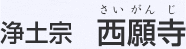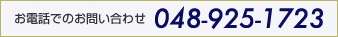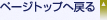月の光 澄みわたる 10月
―Moonlight enters our minds, and we are purified.―
私は田舎に住んでいる。どれほどの田舎かというと、アスファルトの絶対的な量が少なく、航空写真を見てもあたり一面ほぼ山で、広範囲にわたって緑色が広がっている。それに加え、海が近くにあるので、高台から見渡す景色は風光明媚極まりないといったところ。そのおかげ(?)もあり、とても空気が澄んでいて、夜、満月の前後1週間でも月光浴ができるほどである。懐中電灯など、月夜に提灯なのだ。
最近、その月光浴が美容法として注目されている。かのクレオパトラも美しい肌を作るために行っていたらしい。太陽の光には、不安感や憂鬱な気分を解消する働きがあるといわれているが、月の光にも何かしらの浄化作用があるのであろう。
月の光といえば、小学生の頃を思い出す。夏休みの宿題で、新聞の、その日の月の満ち欠けが載っている部分を毎日切り取り、紙に張り付けるというものがあった。当時の私でも、月が満ち欠けすることは知っていたので、「何故、先生はこんなことをさせるのだろう」と幼心に思ったが、先生は、月が約1カ月で地球の周りを1周することを観察させながら、地球の自転と公転を目の当たりにさせようということだったのであろう。
初めは、単に作業としてそれをこなす日々だったが、だんだんとそれが楽しくなり、切り抜きが溜まっていくにつれて、早く完成させたいという気持ちがしだいに増えていった。私は月に1回訪れる満月よりも、月が見えない新月がかっこいいと思っていて、それを切り取る日が来るのを待ち遠しく思い、夜ベランダに出て、その日が来るのを今か今かと待ち続け、月の観察という名の「月光浴」を楽しんでいたのを今でも鮮明に憶えている。
浄土門に帰依している今では、「光」といえば「阿弥陀如来の光明」である。月は自ら光を発することはできないが、太陽の光を反射させ、我々のもとへ柔らかい光を届け続けてくれている。ただひらすら他者に与える存在であり、究極の利他行といえよう。つまり、「月の光」は、慈悲そのものである。太陽は直視できないが、月は眺め続けることができる。慈悲を「みる」ことができるのだ。そして慈悲を感じることで、我々の心の中が輝いてくるのである。
「太陽」が人間の表面を表すとするならば、「月」は人間の内側を表すといえよう。与え続けてくれる存在に身を委ね、それに気付ける心こそが、仏になる教えそのものなのである。
(佐賀県唐津市 專稱寺 齊藤隆沙)