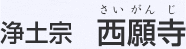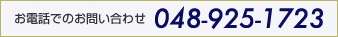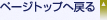思い出話も 供養となる 8月
―Fondly sharing memories is a fine the way to
honor those who have passed away.―
数年前から、高校生に仏教、特に法然上人のご生涯と教えについて授業をするご縁を頂戴しています。
授業の始まる前に、全員でお十念をとなえるようにしています。生徒たちは最初のうち、戸惑いや新鮮さが混ざった表情で周りの声の大きさを窺いながらとなえていますが、梅雨のころには、緊張感が薄れてくるのか、手を叩いてみたり、擦ったり、怠けたりする生徒も出てきます。しかし、それを乗り越え年度末を迎えるころには、自然と全員がしっかりお十念をとなえられるようになっています。習慣の大切さを実感するひと時です。
ある日の授業中に、「家に仏壇がありますか」と尋ねたところ、教室で2、3人しか手が挙がらず、「思っていた以上に少ないなぁ」と感じました。今の10代にとってお仏壇は身近な存在ではなくなりつつあるのでしょうか。
浄土宗のお仏壇には阿弥陀さまのお像や、ご先祖のお位牌などが安置されており、私たちはそこにお花、灯明、お香などをご供養します。法然上人は善導大師の説をうけ、往生浄土のための大切な行である「五種正行」の一つとして、「讃歎供養」を挙げられています。
毎日お線香で供養していると、その香りが家やその人の体に薫じられていき、いつの間にかその家や人の出す香りとなります。仏さま・故人のためにしていた供養の香りが、いつの間にか自分のものとなっているのです。単に香りだけでなく、人生においても同様のことがいえます。
仏教には「薫習」という言葉があり、辞書には「習慣的にしばしば、あるものにはたらきかけるとき、そのものがだんだんとその影響を受ける作用」などとあります。つまり私たちは毎日の習慣のなか、自覚的であるかないかに関わらず、あらゆるものの影響を受け続け、今のようにできあがっているということです。
お盆は「ご先祖のため」にさまざまなご供養をする時期ですが、それと同時にご先祖からどのような影響(薫習)を私たちが受けてきたのかを思い返す機会でもあります。親戚の方と故人の思い出話に花を咲かせることは、「ご先祖のため」の供養であるとともに、たまたま今ある「自分を省みる」ことにもなります。
私たちはどのような薫習を受けてきて、今たまたまこの瞬間に生を受けている者として、これからどのような薫習の縁を頂戴するのでしょうか。
(京都市左京区 大光寺 南宏信)